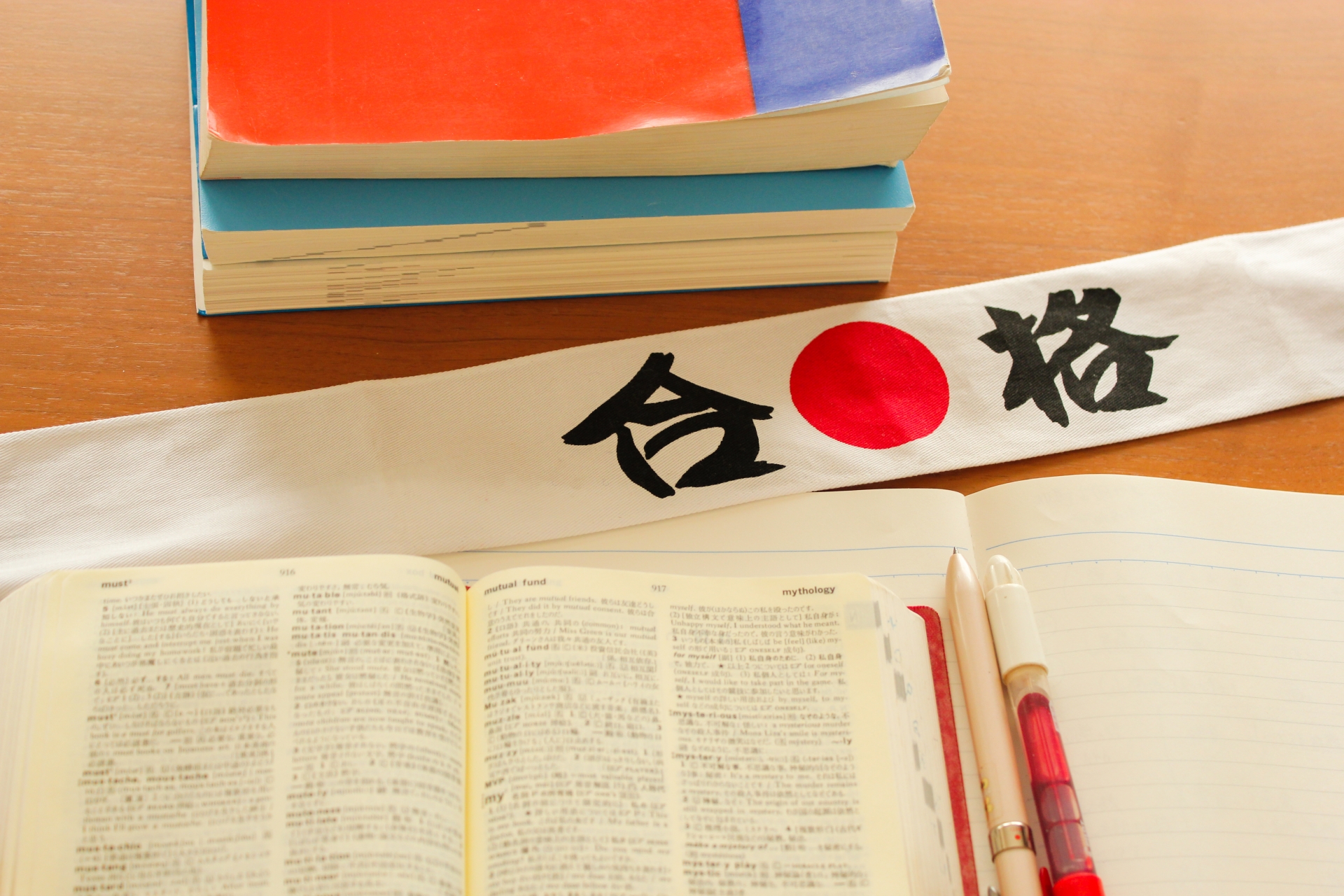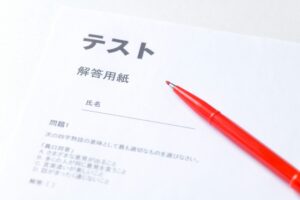2026年度の埼玉県立高校入試まで、残された時間は限られています。しかし、焦る必要はありません。正しい戦略と効率的な学習計画があれば、志望校合格は決して夢ではありません。このページでは、2026年度埼玉県立高校入試を突破するための「必勝の羅針盤」 を提案します。入試の全体像から、具体的な学習スケジュール、そして各教科の対策まで、全てがわかるように構成しました。
受験生本人だけでなく、一番のサポーターである保護者の皆様も、ぜひ最後までお読みください。
2026年度入試の全体像
2026年度(令和8年度)入試日程
埼玉県教育委員会から発表された最新の日程です。まずはこの日から逆算して、すべての計画を立てましょう。
表1:2026年度埼玉県立高等学校入学者選抜 主要日程
| 項目 | 日程 |
| 出願入力期間 | 2026年1月27日(火)~2月10日(火) |
| 出願書類等提出期間 | 2026年2月13日(金)・16日(月)・17日(火) |
| 志願先変更期間 | 2026年2月18日(水)・19日(木) |
| 学力検査 | 2026年2月26日(木) |
| 実技検査・面接 | 2026年2月27日(金) |
| 追検査 | 2026年3月3日(火) |
| 入学許可候補者発表 | 2026年3月6日(金) |
合格の鍵を握る「選抜方法」の基本
埼玉県の公立高校入試は、主に以下の2つの資料を点数化し、その合計点で合否が決まります。
- 学力検査(5教科×100点 = 500点満点):入試当日のテストの点数です。
- 調査書:中学校での成績や活動の記録です。
この「学力検査」と「調査書」の比率は高校・学科によって異なりますが、多くの学校で学力検査が重視される傾向にあります。しかし、だからといって調査書を軽視してはいけません。
侮れない!「調査書(内申点)」の仕組み
調査書の中心となるのが「内申点」です。埼玉県では中学1年生から3年生までの9教科の成績(5段階評定)がすべて評価対象となります。
- 計算方法の主流は「1:1:2」
多中学校3年間の学年ごとの比重は高等学校によって異なり、「1:1:2」や「1:1:3」、「1:2:3」のように、多くの上位校では中学3年生の成績がより重視される傾向にあります。多くの学校で、(中1の9教科合計)+(中2の9教科合計)+(中3の9教科合計 × 2) という計算方法が採用されており、中学3年生の成績が2倍になるため、3年生での頑張りが非常に重要になります。 - 「特別活動等の記録」も加点対象に
生徒会活動や部活動での実績、英検®などの資格も評価の対象となります。ボランティアへの参加や、習い事等での入賞や受賞歴など、学校の内外での積極的な活動が、合格を後押ししてくれることがあります。
入学試験は、多くの場合「第1次選抜」と「第2次選抜」の2段階で行われます。ここで重要なのは、学力検査と調査書の得点比率が段階によって変動する点です。例えば、第1次選抜で「学力検査:調査書」の比率が「6:4」であったものが、第2次選抜では「7:3」に変更されることがあります。これは、募集定員の残りの枠を争う段階では、より学力検査の結果が重視されることを意味します。このことを理解しておくことは、受験戦略を立てる上で重要な要素であり、中学校生活を通じた継続的な努力(内申点対策)と、入試本番での5時間にわたる集中力(学力検査対策)の両方が不可欠であることを示しています。
この仕組みを具体的に理解するため、異なるタイプの高等学校の選抜基準を知っておくことが有効です。
表2:主要高等学校における選抜基準の比較分析(令和8年度)
| 学校名 (学科) | 選抜段階 | 定員割合 | 学力検査: 調査書 比率 | 中1:中2:中3 比率 | 特別活動等の記録 | その他の項目 |
| 浦和 (普通) | 第1次 | 60% | 500 : 334 | 1:1:2 | 40点 | 100点 |
| 第2次 | 40% | 500 : 215 | ||||
| 大宮 (理数) | 第1次 | 60% | 700 : 467 | 1:1:2 | 70点 | 110点 |
| 第2次 | 40% | 700 : 300 | ||||
| 春日部 (普通) | 第1次 | 60% | 500 : 334 | 1:2:4 | 5点 | 180点 |
| 第2次 | 39% | 500 : 215 | ||||
| 越谷北 (普通) | 第1次 | 60% | 500 : 335 | 1:1:2 | 70点 | 20点 |
| 第2次 | 40% | 500 : 216 | ||||
| 浦和商業 (商業) | 第1次 | 80% | 500 : 500 | 1:1:2 | 40点 | 30点 |
| 第2次 | 20% | 500 : 750 | ||||
| 川越工業 (共通) | 第1次 | 80% | 500 : 500 | 1:1:2 | 30点 | 60点 |
| 第2次 | 20% | 500 : 750 |
また、これまで「3 特別活動等の記録」に記載されていた部活動に関する記述が、「5 その他の項目」へ移行されました。これに伴い、各高等学校は選抜基準を見直し、「その他の項目」の配点を増加させる傾向が見られます。部活動が、英検や漢検といった資格取得と同列の「その他の項目」に位置づけられたことは、評価の視点が「参加したこと」から「具体的な成果を上げたこと」へとシフトしていることを示唆しています。実際に、浦和高校の選抜基準では、「その他の項目」における部活動評価について、関東大会や全国大会といった大会レベルや、レギュラーとしての出場実績などが具体的に点数化の基準として明記されています。これは、漠然と「3年間部活動を続けた」という実績よりも、「県大会ベスト8にレギュラーとして貢献した」といった定量的で客観的な成果がより高く評価される時代の到来を意味しています。
レベル別問題「学校選択問題」とは?
浦和高校、大宮高校、川越高校など、学力上位校の一部(22校)では、数学と英語で難易度の高い「学校選択問題」が採用されています。中学校の学習指導要領に準拠した基礎的な内容に加え、複数の単元の知識を合わせた、思考力、判断力、表現力といった応用的で高い能力を測定することを目的とした内容で構成されます。志望校がこの問題を採用しているかどうかは、必ず事前に確認しましょう。
合格への年間ロードマップ!時期別学習スケジュール
「いつ、何をすればいいの?」という疑問に、明確な道筋を示します。
【中学3年生 1学期(4月~7月)】基礎固め期
テーマ:中学1・2年の総復習と学校の授業の完全理解
やるべきこと:
- まずは、これまでの学習範囲で苦手な単元、曖昧な部分をリストアップします。
- 各教科、教科書レベルの基礎問題を徹底的に反復し、完璧に解けるようにしましょう。
- 学校の定期テストでは、自己最高点を狙う意識で臨み、内申点アップに繋げます。
- 学習習慣の確立がこの時期最大のミッションです。「平日2時間、休日4時間」など、自分なりのルールを決めて机に向かいましょう。
【夏休み(8月)】飛躍の勝負期
テーマ:全範囲の総復習と苦手分野の完全克服
やるべきこと:
- 1・2年生の復習を終わらせ、3年生の1学期までの内容も含めた全範囲の総復-習に着手します。
- 苦手分野には、集中的に時間を投下します。例えば「数学の関数」「英語の関係代名詞」など、大きなテーマを決めて、参考書1冊を完璧にするくらいの意気込みで取り組みましょう。
- 1日6~8時間の学習時間を目標に、計画的かつ集中的な勉強で、ライバルに差をつけましょう。
【中学3年生 2学期(9月~12月)】実践力養成期
テーマ:入試過去問演習と得点力の向上
やるべきこと:
- いよいよ埼玉県立高校の過去問(過去問)に取り組み始めます。まずは3~5年分を解き、出題形式や時間配分を体感しましょう。
- 解きっぱなしはNG。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、**「解き直しノート」**を作成します。
- 学校の授業も疎かにせず、内申点を確定させる最後の定期テストに全力を注ぎます。
【冬休み~入試直前期(1月~2月)】最終仕上げ期
テーマ:時間配分とミスの撲滅、そして自信の醸成
やるべきこと:
- 本番と全く同じ時間配分で過去問を繰り返し解き、**「時間内に解き切る力」**を体に染み込ませます。
- 「解き直しノート」を何度も見返し、自分の弱点を完全に潰します。新しい問題集に手を出すより、これまでやってきたことの精度を高める方が効果的です。
- 体調管理も重要な受験対策です。十分な睡眠と栄養を心がけ、万全の状態で本番を迎えられるようにしましょう。
教科別徹底対策!5教科必勝勉強法
ここからは、各教科の具体的な攻略法を伝授します。
国語:時間配分と読解の「型」が命
- 出題傾向:小説・物語文、論説・説明文、古文、漢字・語彙・文法という構成が基本。文章量が多く、時間内に正確に読み解く力が必要です。
- 必勝ポイント:
1.時間を意識した読解練習:大問ごとに時間を区切って過去問を解き、自分なりの時間配分を見つけましょう。
2.古文は得点源:「歴史的仮名遣い」などの基本ルールを覚え、主語が誰なのかを意識して読めば、安定して得点でき
ます。
3.記述問題の対策:解答の根拠となる部分を本文中から見つける練習を重ねましょう。「〜ということ。」「〜から。」な
ど、設問に合わせた文末表現を意識することも大切です。
数学:大問1の攻略が合格への最短ルート
- 出題傾向:大問1は計算・小問集合で配点が高い。後半には作図や証明、関数、図形の応用問題が出題されます。学校選択問題は、解法を複数組み合わせるような思考力問題が特徴です。
- 必勝ポイント:
1.大問1は満点を狙う:ここの計算問題や一行問題でミスをしないことが高得点の絶対条件。毎日少しずつでも計算練習
を続け、速さと正確性を両立させましょう。
2.作図と証明は「暗記」から:基本的な作図方法や証明の「型」(合同条件や相似条件の使い方)は、まず書き方を覚え
てしまいましょう。そこから応用問題に取り組むのが効率的です。
3.(学校選択問題)「なぜそうなるか」を追求する:公式をただ覚えるだけでなく、その公式が成り立つ理由まで理解す
ることで、初見の問題にも対応できる応用力が身につきます。
英語:単語・文法という土台の上に長文力を
- 出題傾向:リスニング、対話文、長文読解、英作文とバランスの取れた構成。長文の語数が多く、速読力が求められます。学校選択問題は、文章のテーマがより高度になり、語彙レベルも上がります。
- 必勝ポイント:
1.リスニングは「先読み」:音声が流れる前に、設問と選択肢に目を通し、何を聞き取るべきかを予測しておくことが
高得点のカギです。
2.長文読解は「音読」で:日頃から教科書や長文問題を声に出して読むことで、英語を英語のまま理解するスピードが
格段に上がります。
3.英作文は「基本例文のストック」:自分の意見を書く問題では、まず使える表現(I think that…, I have two
reasons.など)を覚え、それに単語を当てはめて書く練習から始めましょう。
理科:全分野を網羅する「広く浅い」知識が武器
- 出題傾向:物理・化学・生物・地学の4分野から、ほぼ均等に出題されます。実験や観察に基づいた思考力問題が多いのが特徴です。
- 必勝ポイント:
1.苦手分野を作らない:全分野から出題されるため、特定の分野を捨てるのは非常に危険です。夏休みまでに、すべて
の単元の基礎を漏れなく復習しましょう。
2.実験・観察の「目的と手順」を理解する:なぜこの操作をするのか、この結果から何が言えるのか、というプロセス
をセットで覚えることが、単なる暗記で終わらないためのコツです。
3.計算問題は公式の理解から:オームの法則や密度など、頻出の計算問題は、まず公式の意味をしっかり理解し、単位
に注意しながら演習を重ねましょう。
社会:歴史は「流れ」、地理は「関連付け」で攻略
- 出題傾向:地理・歴史・公民の3分野から出題。地図や年表、グラフなどの資料を読み解く問題が非常に多いのが特徴です。
- 必勝ポイント:
1.歴史は「タテの流れ」を意識:「なぜその出来事が起きたのか」「その出来事が次にどう繋がるのか」という因果関係
を意識すると、知識が定着しやすくなります。特に江戸時代は頻出です。
2.地理は「なぜ?」で考える:「なぜこの地域ではこの産業が盛んなのか?」(気候や地形と関連付けて考える)など、
理由をセットで覚えることで、資料問題に対応できる力がつきます。
3.記述問題は「キーワード」を盛り込む:指定された語句を使って説明する問題が頻出します。教科書の太字の語句の
意味を、簡潔に説明できる練習をしておきましょう。
まとめ:保護者の方へ、そして受験生の君へ
保護者の皆様へ
受験は、お子様にとって大きな試練であると同時に、精神的に大きく成長する機会でもあります。結果だけに目を向けるのではなく、日々の努力のプロセスを認め、励ましてあげてください。「勉強しなさい」よりも「いつも頑張っているね」の一言が、何よりの力になります。
そして、食事や睡眠など、お子様が最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりにご協力をお願いいたします。ご家庭が、お子様にとって心安らげる「安全基地」であることが、合格への一番の近道です。
受験生のみんなへ
今、君の前には志望校合格という大きな山がそびえ立っているように見えるかもしれません。不安で、押しつぶされそうになる日もあるでしょう。
しかし、忘れないでください。今日からでも一歩ずつ、着実に努力を重ねていけば、その山の頂上には必ずたどり着けます。大切なのは、他人と比べることではありません。昨日の自分より少しでも成長することです。解けなかった問題が一つ解けるようになった。覚えられなかった単語を一つ覚えた。その小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな自信となり、君を合格へと導いてくれます。
君の可能性は無限大です。自分を信じて、未来を切り拓くための挑戦を、私たちも全力で応援しています。
さあ、一緒に頑張りましょう!