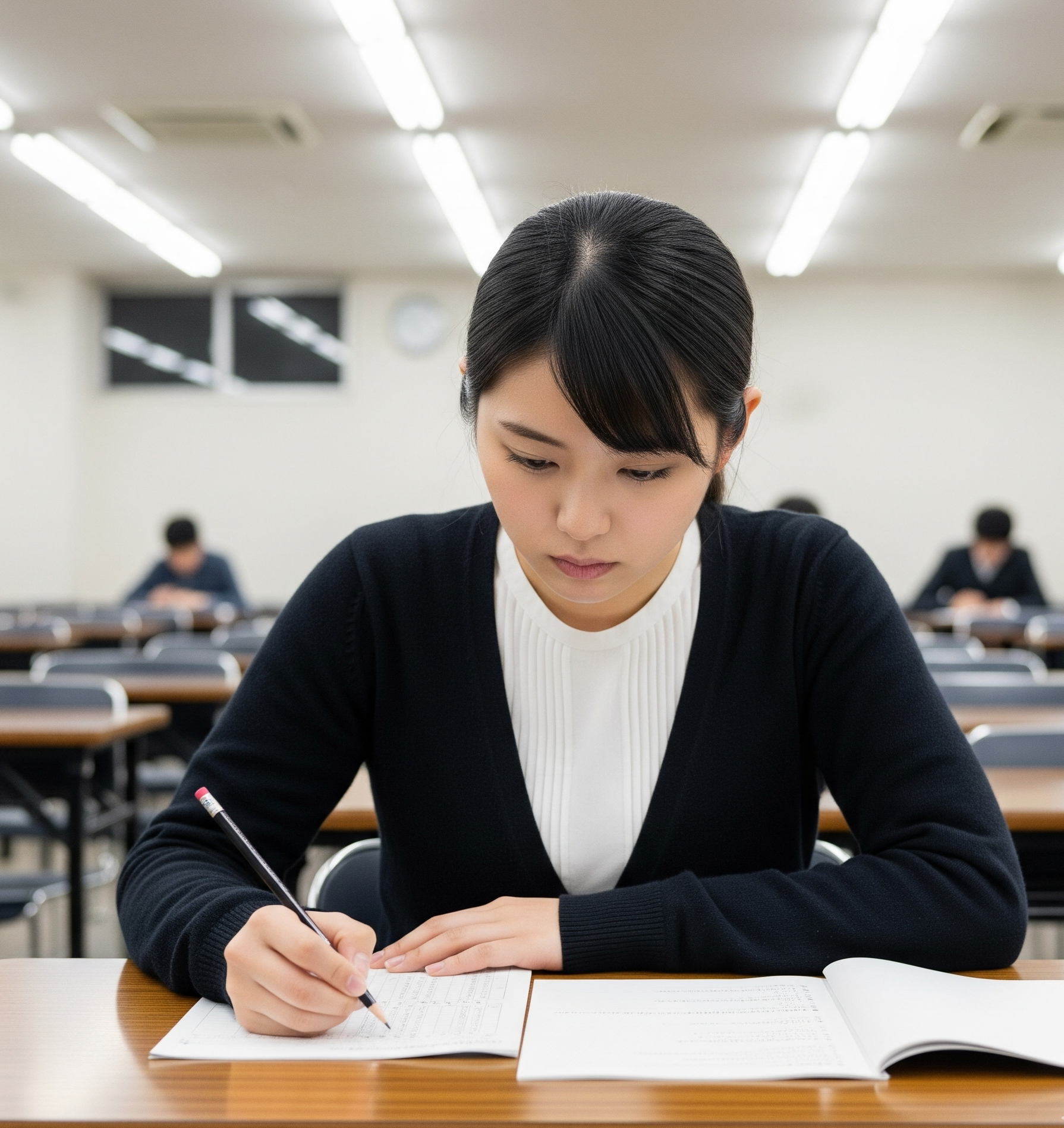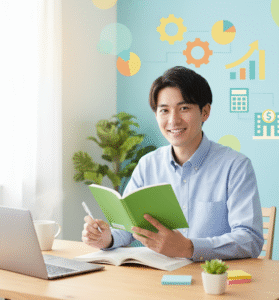はじめに:簿記3級合格への第一歩
日商簿記3級の学習を始めたばかりの多くの方が、「借方(かりかた) 」 「貸方(かしかた) 」といった専門用語の壁に直面します 。しかし、簿記3級は決して難解な資格ではなく、企業の経済活動を記録・計算・整理するための実践的なスキルであり、経理や事務職はもちろん、さまざまな業界で役立つ強力な武器となります 。このガイドは、難しそうに見える簿記の世界を、初心者の方でも体系的に理解し、自信を持って試験に臨めるように構成されています。
「過去問」に関する重要な注意点
本ガイドを進める前に、一つ重要な点をお伝えします。2021年度から日商簿記検定は、従来の統一筆記試験に加えて、随時受験可能なネット試験(CBT方式)が導入されました。この変更に伴い、CBT方式では受験者ごとに異なる問題が出題されるため、公式な「過去問題」は公開されなくなりました 。
そこで、本ガイドでは、試験の出題傾向を最も正確に反映している日本商工会議所(JCCI)が公式に提供する「サンプル問題」を徹底的に分析・解説します 。これらのサンプル問題は、実際の試験レベルと同等であり、合格に必要な知識と解法テクニックを網羅的に学習するための最適な教材です。
本ガイドの構成と学習の進め方
日商簿記3級の試験は、大きく分けて3つの大問で構成されています 。
- 第1問:仕訳問題 (配点45点)
- 第2問:勘定記入・補助簿など (配点20点)
- 第3問:決算整理・財務諸表作成 (配点35点)
本ガイドもこの構成に沿って、各大問のサンプル問題を解きながら、単なる解答の提示だけでなく、その背景にある簿記の基本原則から、試験で高得点を取るための戦略的思考プロセスまでを詳しく解説します。
簿記学習で挫折する主な原因は、知識不足だけでなく、専門用語への苦手意識や、自分が今何のためにこの作業をしているのかという全体像の喪失感にあります 。このガイドは、そうした心理的な障壁を取り除くことを目指します。取引が発生してから財務諸表が完成するまでの一連の流れを明確な「地図」として示し、一つひとつの専門用語を具体的なビジネスシーンと結びつけながら解説することで、丸暗記ではない本質的な理解へと導きます 。
【配点45点】第1問「仕訳問題」を完全マスターする
なぜ第1問が合否を分けるのか
日商簿記3級において、第1問の仕訳問題は単なる一つの大問ではありません。全100点満点のうち45点を占める最重要セクションであり、ここでの出来が合否を直接左右します 。全15問出題される仕訳問題は、簿記のすべての基本が凝縮されており、「仕訳ができないと話にならない」と言われるほど、後続の問題を解くための土台となります 。
第1問の重要性は、その配点の高さだけにとどまりません。簿記の学習プロセスは、個々の取引を「仕訳」という会計言語に翻訳することから始まります。この最初のステップでつまずくと、その後の第2問(勘定への転記)や第3問(財務諸表の作成)で「芋づる式失点」を引き起こすことになります 。例えば、第1問で仕訳を間違えれば、その誤った情報をもとに総勘定元帳へ転記することになり、第2問も不正解となります。さらに、その誤った勘定残高を使って決算整理を行えば、最終的に作成する損益計算書や貸借対照表の数値もすべて狂ってしまい、第3問で壊滅的な失点を招く可能性があります。
したがって、第1問をマスターすることは、単に45点を確保するためだけでなく、試験全体の安定した得点力を築くための絶対条件なのです。このセクションでは、どんな取引にも対応できる盤石な思考プロセスを身につけることを目指します。
仕訳サンプル問題
ここでは、典型的な取引パターンを網羅したサンプル問題を3つ取り上げ、独自の5ステップ構成で詳細に解説します。
問題1:付随費用を含む商品の仕入
商品5,000円を仕入れ、代金は以前に支払っていた手付金500円を差し引き、残額は掛けとした。なお、商品発送にかかる運送費400円は現金で支払った。
解答
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 仕入 | 5,400 | 前払金 | 500 |
| 買掛金 | 4,500 | ||
| 現金 | 400 |
1. 詳しい解説
この問題を解く鍵は、取引を正確に分解し、体系的に整理することです。ここでは、初心者でも間違いなく仕訳ができる「取引分析表」を用いて解説します。
- ステップ 1:取引の要素を分解する 問題文を丁寧に読み解き、取引の要素を洗い出します。「商品5,000円を仕入れ」→商品の購入、「手付金500円を差し引き」→前払金の充当、「残額は掛け」→買掛金の発生、「運送費400円は現金で支払い」→付随費用の支払い、という4つの要素に分解できます 。
- ステップ 2:取引分析表で整理する 次に、各要素が勘定科目の5大要素(資産、負債、純資産、収益、費用)のどれに該当し、どのように増減したかを整理します。これが仕訳の最も重要なプロセスです。
| 勘定科目 | 5要素 | 増減 | 借方/貸方 | 金額 | 解説 |
| 仕入 | 費用 | 増加 | 借方 | 5,400 | 商品本体の価格5,000円に、仕入にかかった運送費(仕入諸掛)400円を加えた金額が仕入原価となる。費用の発生は借方に記入する。 |
| 前払金 | 資産 | 減少 | 貸方 | 500 | 以前に支払った手付金(前払金という資産)が、今回の仕入に充当されたため減少した。資産の減少は貸方に記入する。 |
| 買掛金 | 負債 | 増加 | 貸方 | 4,500 | 商品代金の残額(5,000円 – 500円)は後払いなので、将来支払う義務(買掛金という負債)が増加した。負債の増加は貸方に記入する。 |
| 現金 | 資産 | 減少 | 貸方 | 400 | 運送費を現金で支払ったため、現金(資産)が減少した。資産の減少は貸方に記入する。 |
この表を使うことで、なぜその勘定科目が借方または貸方にくるのか、その理由(5要素の増減ルール)が明確になります [1, 11]。また、最終的に借方合計(5,400)と貸方合計(500 + 4,500 + 400 = 5,400)が必ず一致するという「貸借平均の原理」を確認でき、ケアレスミスを防ぐことができます [8]。
2. 関連論点の解説
この問題の核心は「仕入諸掛(しいれしょがかり)」の扱いです。仕入諸掛とは、商品を仕入れる際に付随して発生する費用(運送費、保険料、関税など)のことです。会計ルールでは、これらの費用は商品の取得原価に含めて処理します。
- 当店負担の仕入諸掛:今回の問題のように、購入者(当店)が運送費を負担した場合、その費用は「仕入」勘定に含めます。
- 先方負担の仕入諸掛:もし売主が運送費を負担する契約で、当店が一時的に立て替えて支払った場合は、「立替金」(資産)として処理し、仕入勘定には含めません。
逆に、商品を販売した際に発生する運送費(売上諸掛)は、「発送費」(費用)という別の勘定科目で処理し、売上勘定には含めません。この違いは試験で頻出する論点なので、明確に区別できるようにしておきましょう。
3. 学習のポイントや注意点
- ポイント:商品仕入の際は、必ず運送費などの「付随費用」がないかを確認し、あれば取得原価に含めることを忘れないでください。
- 注意点:問題文に「以前に〜だったが、本日〜」といった過去の取引情報が含まれていることがあります 。仕訳の対象は「本日」の取引です。惑わされないように、取引の日付を強く意識して問題を読む習慣をつけましょう。
サンプル問題2:収入印紙の購入
郵便局で収入印紙3,000円分を購入し、代金は現金で支払った。なお、この収入印紙はただちに使用した。
解答
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
1. 詳しい解説
この問題は、一見シンプルですが、勘定科目の選択で迷いやすい典型的な問題です。
- ステップ 1:取引の要素を分解する 「収入印紙3,000円分を購入し、使用した」→費用の発生、「代金は現金で支払った」→資産の減少、という2つの要素に分解できます。
- ステップ 2:取引分析表で整理する
| 勘定科目 | 5要素 | 増減 | 借方/貸方 | 金額 | 解説 |
| 租税公課 | 費用 | 増加 | 借方 | 3,000 | 収入印紙は印紙税という税金の一種。このように国や地方公共団体に納める税金や、公的な手数料などを支払った場合は「租税公課」という費用勘定で処理する 。費用の発生は借方に記入する。 |
| 現金 | 資産 | 減少 | 貸方 | 3,000 | 現金で支払ったため、現金(資産)が減少した。資産の減少は貸方に記入する。 |
「消耗品費」と間違えやすいですが、収入印紙や固定資産税、自動車税などは税金(租税)や公的な負担金(公課)の性質を持つため、「租税公課」が適切な勘定科目となります。
2. 関連論点の解説
この問題のポイントは「ただちに使用した」という点です。もし、決算対策などで収入印紙や切手をまとめて購入し、期末時点で未使用分が残っている場合、その未使用分は費用ではなく資産として扱います。
- 購入時: (借) 租税公課 10,000 / (貸) 現金 10,000 (全額を費用として処理)
- 決算整理時(未使用分が2,000円あった場合): (借) 貯蔵品 2,000 / (貸) 租税公課 2,000 この仕訳により、当期の費用(租税公課)から未使用分2,000円を減額し、それを「貯蔵品」という資産勘定に振り替えます。これにより、費用と資産が正しく期間配分されます。
3. 学習のポイントや注意点
- ポイント:収入印紙、固定資産税、印鑑証明書の発行手数料などは「租税公課」で処理すると覚えましょう。
- 注意点:問題文に「ただちに使用した」か「保管している」かの一文があるかで、処理が大きく変わる可能性があります。特に決算整理問題では、この「貯蔵品」への振替が頻出論点となるため注意が必要です。
サンプル問題3:貸倒れの処理
得意先の神奈川商店が倒産し、同社に対する売掛金150,000円が貸し倒れた。この売掛金のうち50,000円は前期に販売したものであり、残額は当期に販売したものである。なお、貸倒引当金の残高は60,000円である。
解答
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 貸倒引当金 | 50,000 | 売掛金 | 150,000 |
| 貸倒損失 | 100,000 |
1. 詳しい解説
貸倒れの問題は、①いつ発生した売掛金か、②貸倒引当金の残高はいくらか、の2点が最大のポイントです。
- ステップ 1:取引の要素を分解する 「売掛金150,000円が貸し倒れた」→売掛金(資産)の減少。「前期発生分50,000円」と「当期発生分100,000円」に分けて考える必要があります。
- ステップ 2:取引分析表で整理する
| 勘定科目 | 5要素 | 増減 | 借方/貸方 | 金額 | 解説 |
| 貸倒引当金 | 資産のマイナス | 減少 | 借方 | 50,000 | 前期発生の売掛金が貸し倒れた場合、そのために設定しておいた貸倒引当金(残高60,000円)を取り崩して充当する。今回は50,000円なので、全額を引当金でカバーできる。 |
| 貸倒損失 | 費用 | 増加 | 借方 | 100,000 | 当期発生の売掛金が貸し倒れた場合は、貸倒引当金は使わずに、直接「貸倒損失」という費用勘定で処理する。 |
| 売掛金 | 資産 | 減少 | 貸方 | 150,000 | 回収不能となったため、売掛金(資産)が150,000円減少した。資産の減少は貸方に記入する。 |
この問題のロジックは以下の通りです。
1. 貸倒引当金は、前期末に「前期以前に発生した売掛金」が将来貸し倒れることを見越して設定したものです。
2. したがって、前期発生の売掛金が貸し倒れた場合は、まずこの引当金を使います。もし引当金残高を超える分があれば、その超過分は「貸倒損失」(費用)となります。
3. 一方、当期に発生した売掛金については、まだ貸倒引当金が設定されていません。そのため、それが貸し倒れた場合は、全額を当期の費用(貸倒損失)として処理するしかありません。
2. 関連論点の解説
貸倒れに関する処理は、発生時だけでなく、決算時の貸倒引当金設定もセットで理解することが重要です。
決算時には、期末に残っている売掛金や受取手形などの債権残高に対して、一定の割合(貸倒実績率など)を乗じて、翌期に発生するかもしれない貸倒れに備えるための引当金を設定します。
- 例:期末の売掛金残高が1,000,000円、貸倒実績率が2%、決算整理前の貸倒引当金残高が5,000円の場合。
- 必要な引当金:1,000,000×2%=20,000円
- 現在の残高:5,000円
- 追加で設定する額(差額補充法):20,000−5,000=15,000円
- 決算整理仕訳: (借) 貸倒引当金繰入 15,000 / (貸) 貸倒引当金 15,000 「貸倒引当金繰入」は費用勘定です。
3. 学習のポイントや注意点
- ポイント:貸倒れの問題が出たら、まず「前期発生分」か「当期発生分」かを問題文から見つけ出すことが最優先です。
- 注意点:PC販売業を営む会社が「販売用のパソコン」を購入した場合、それは「備品」(固定資産)ではなく「仕入」(費用)です 。このように、企業の業種によって勘定科目の意味合いが変わる「先入観」を狙ったひっかけ問題に注意しましょう。
【配点20点】第2問「勘定記入・補助簿」の得点力を上げる
「寄せ集め問題」の攻略法
第2問は、配点20点でありながら、勘定記入(T勘定)、補助簿の選択、語句の穴埋めなど、様々な形式の問題が出題されるため、「寄せ集め問題」や「福袋問題」とも呼ばれます 。出題範囲が広く対策が立てにくいため、多くの受験生が苦手意識を持っています 。
戦略としては、試験時間が60分と短いことを考慮し、配点の高い第1問(45点)と第3問(35点)を優先的に解き、残った時間で第2問に取り組むのが効率的です 。ただし、完全に捨てるべきではありません。第2問は満点を狙うのが難しい反面、基本的な知識で確実に取れる部分点も存在します。
このセクションで問われている能力の根底にあるのは、一つ一つの「仕訳」が、どのように会計システム全体(総勘定元帳や補助簿)に記録され、繋がっていくのかという「取引データの流れ」を理解しているか、という点です。仕訳は取引の時系列記録ですが、勘定口座(T勘定)は特定の勘定科目ごとの増減をまとめた記録です。この、仕訳帳から総勘定元帳へ記録を書き写すプロセスを「転記」と呼びます。第2問は、この「転記」のプロセスを正確に理解しているかを、様々な角度から問う問題なのです。
サンプル問題の徹底分析:前払家賃の勘定記入
以下の取引に基づき、前払家賃勘定に必要な記入を行い、締め切りなさい。会計期間はX4年4月1日からX5年3月31日までである。
- X4年4月1日:前期末に計上した前払家賃25,000円について再振替仕訳を行った。
- X4年9月1日:事務所の家賃1年分300,000円を普通預金から振り込んだ。家賃は毎年9月1日に1年分を前払いしている。
- X5年3月31日:決算にあたり、家賃の未経過分を月割計算により計上した。
解答
| 日付 | 相手勘定科目 | 金額 | 日付 | 相手勘定科目 | 金額 |
| X4/4/1 | 前期繰越 | 25,000 | X4/4/1 | 支払家賃 | 25,000 |
| X5/3/31 | 支払家賃 | 125,000 | X5/3/31 | 次期繰越 | 125,000 |
| 合計 | 150,000 | 合計 | 150,000 | ||
| X5/4/1 | 前期繰越 | 125,000 |
1. 詳しい解説
この問題を解くには、各日付の取引をまず仕訳に変換し、それをT勘定に転記するというステップを踏みます。
- ステップ1:各取引を仕訳に変換する
- X4年4月1日(再振替仕訳) 前期末の決算整理で「(借) 前払家賃 25,000 / (貸) 支払家賃 25,000」という仕訳が行われています。「再振替仕訳」とは、期首にこの逆の仕訳を行うことです 。 (借) 支払家賃 25,000 / (貸) 前払家賃 25,000
- X4年9月1日(家賃支払い) この時点では、支払った全額を費用として処理します。 (借) 支払家賃 300,000 / (貸) 普通預金 300,000 (この仕訳は「前払家賃」勘定には直接影響しません)
- X5年3月31日(決算整理仕訳) X4年9月1日に支払った家賃300,000円は、X5年8月31日までの1年分です。当期(X5年3月31日まで)に対応するのは7ヶ月分(9月〜3月)、翌期に対応するのは5ヶ月分(4月〜8月)です。この翌期分を当期の費用から除き、資産(前払家賃)として計上します。
- 前払い分(未経過分)の計算: 300,000×12ヶ月5ヶ月=125,000円
- 決算整理仕訳: (借) 前払家賃 125,000 / (貸) 支払家賃 125,000
- X4年4月1日(再振替仕訳) 前期末の決算整理で「(借) 前払家賃 25,000 / (貸) 支払家賃 25,000」という仕訳が行われています。「再振替仕訳」とは、期首にこの逆の仕訳を行うことです 。 (借) 支払家賃 25,000 / (貸) 前払家賃 25,000
- ステップ 2:仕訳からT勘定へ転記する(データの流れを可視化)
仕訳が完了したら、それを「前払家賃」のT勘定に書き写します。
- 前期繰越:まず、期首時点での残高を借方に「前期繰越 25,000」と記入します。資産勘定のホームポジションは借方だからです。
- 4月1日の仕訳:「(貸) 前払家賃 25,000」とあるので、T勘定の貸方に日付と相手勘定科目「支払家賃」、金額25,000を記入します。
(仕訳の貸方) → (T勘定の貸方) - 3月31日の仕訳:「(借) 前払家賃 125,000」とあるので、T勘定の借方に日付と相手勘定科目「支払家賃」、金額125,000を記入します。
(仕訳の借方) → (T勘定の借方) - 締め切り:最後に勘定を締め切ります。借方合計 (25,000 + 125,000 = 150,000) と貸方合計 (25,000) の差額 (125,000) が、翌期に繰り越される残高です。これを貸方の空いている側に「次期繰越 125,000」と記入し、借方と貸方の合計額を一致させます。最後に、翌期の期首(X5年4月1日)に、借方に「前期繰越 125,000」と記入して完了です 。
- 前期繰越:まず、期首時点での残高を借方に「前期繰越 25,000」と記入します。資産勘定のホームポジションは借方だからです。
2. 関連論点の解説
この問題は「費用の前払い(繰延べ)」という決算整理事項の一つです。決算整理では、他にも以下の3つのパターンが頻出します。これらはセットで理解しておくと、応用力が格段に向上します 。
- 費用の未払い(見越し):例)当期分の利息だが、支払いは翌期。→「未払利息」(負債)を計上。
- 収益の未収(見越し):例)当期分の受取利息だが、入金は翌期。→「未収収益」(資産)を計上。
- 収益の前受け(繰延べ):例)翌期分の家賃を当期に受け取った。→「前受収益」(負債)を計上。
また、第2問では補助簿の選択問題も出題されます 。これは、「ある取引が発生した際に、記入が必要な補助簿をすべて選びなさい」という形式の問題です。例えば、「商品を掛けで仕入れ、一部を現金で支払った」場合、記入が必要な補助簿は「仕入帳」「現金出納帳」「買掛金元帳」「商品有高帳」となります。各補助簿が「何を記録するための帳簿なのか」という役割を理解しておくことが重要です。
3. 学習のポイントや注意点
- ポイント:T勘定への転記は、「仕訳の借方にある勘定科目は、T勘定の借方へ」「仕訳の貸方にある勘定科目は、T勘定の貸方へ」というルールを徹底することです。
- 注意点:日付の重要性を再認識してください。「期首」「期中」「期末」の日付によって、行うべき処理(再振替仕訳、期中取引、決算整理仕訳)が全く異なります。
【配点35点】第3問「決算整理」で合格を掴む
ラスボスを制す「体系的なワークフロー」
配点35点を占める第3問は、貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)の作成、精算表作成、決算整理後残高試算表作成のいずれかが出題される総合問題です 。これまでに学んだすべての簿記スキルを結集して解く、まさに試験の「ラスボス」です。一見すると、その情報量の多さに圧倒されがちですが、実際には非常に構造化されたプロセスドリブンな問題です。合格の鍵は、ひらめきや天才的な計算能力ではなく、ミスなく着実に作業を進めるための「体系的なワークフロー」を確立することにあります。
この大問で最も恐ろしいのは、第1問の解説でも触れた「芋づる式失点」です 。第3問は、与えられた試算表の数値に、複数の決算整理事項を加味して最終的な財務諸表を完成させるという多段階のプロセスを辿ります。この過程で、例えば減価償却費の計算を一つ間違えるだけで、その後の減価償却累計額、当期純利益、繰越利益剰余金、資産合計、純資産合計といった関連するすべての数値が連鎖的に誤り、大量失点に繋がります。
さらに、試験時間60分という厳しい制約が、このリスクを増大させます 。焦りはケアレスミスを誘発し、小さな計算ミスが致命的な結果を招くのです 。したがって、このセクションでは、知識そのものよりも、時間内に正確に解答を導き出すための「エラーを防ぐための作業手順」を徹底的に解説します。
サンプル問題の徹底分析:精算表の作成
GOUKAKU商店(個人企業)の以下の決算整理前残高試算表および期末決算整理事項に基づいて、精算表を完成させなさい。会計期間はX1年4月1日からX2年3月31日までの1年間である。
【決算整理前残高試算表】GOUKAKU商店決算整理前残高試算表X2年3月31日
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| 現金 | 150,000 | |
| 当座預金 | 380,000 | |
| 売掛金 | 500,000 | |
| 繰越商品 | 200,000 | |
| 備品 | 800,000 | |
| 買掛金 | 400,000 | |
| 借入金 | 500,000 | |
| 資本金 | 1,000,000 | |
| 売上 | 2,500,000 | |
| 仕入 | 1,950,000 | |
| 給料 | 320,000 | |
| 通信費 | 100,000 | |
| 合計 | 4,400,000 | 4,400,000 |
【期末決算整理事項】
- 期末商品棚卸高は ¥300,000 であった。売上原価は仕入の行で計算すること。
- 売掛金の期末残高に対して、2%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。
- 備品について、残存価額ゼロ、耐用年数10年の定額法により減価償却を行う。
- 給料の未払分が ¥30,000である。
1. 解答
精算表
| 勘定科目 | 試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 |
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現金 | 150,000 | |||
| 当座預金 | 380,000 | |||
| 売掛金 | 500,000 | |||
| 繰越商品 | 200,000 | (2) 300,000 | (1) 200,000 | |
| 備品 | 800,000 | |||
| 買掛金 | 400,000 | |||
| 借入金 | 500,000 | |||
| 資本金 | 1,000,000 | |||
| 売上 | 2,500,000 | |||
| 仕入 | 1,950,000 | (1) 200,000 | (2) 300,000 | |
| 給料 | 320,000 | (4) 30,000 | ||
| 通信費 | 100,000 | |||
| 小計 | 4,400,000 | 4,400,000 | ||
| 貸倒引当金繰入 | (3) 10,000 | |||
| 貸倒引当金 | (3) 10,000 | |||
| 減価償却費 | (4) 80,000 | |||
| 備品減価償却累計額 | (4) 80,000 | |||
| 未払給料 | (5) 30,000 | |||
| 修正記入合計 | 620,000 | 620,000 | ||
| 当期純利益 | ||||
| 合計 |
解説
【ステップ1】決算整理仕訳を行う
まず、決算整理事項を一つずつ仕訳にしていきます。この仕訳がすべての基本となります。
1. 売上原価の算定 「しー、くり、くり、しー」の仕訳を思い出しましょう。
- 期首商品(決算整理前残高試算表の繰越商品)を仕入勘定に振り替えます。
- (借) 仕入 200,000 / (貸) 繰越商品 200,000
- 期末商品(決算整理事項1)を仕入勘定から繰越商品勘定に振り替えます。
- (借) 繰越商品 300,000 / (貸) 仕入 300,000
2. 貸倒引当金の設定
- 貸倒引当金の設定額を計算します。
- 売掛金期末残高 ¥500,000 × 2% = ¥10,000
- 決算整理前残高試算表に貸倒引当金はないため、計算した全額を繰り入れます。
- (借) 貸倒引当金繰入 10,000 / (貸) 貸倒引当金 10,000
3. 減価償却
- 減価償却費を計算します。
- 取得原価 ¥800,000 ÷ 耐用年数 10年 = ¥80,000
- 備品を直接減らすのではなく、備品減価償却累計額という勘定科目を使います。
- (借) 減価償却費 80,000 / (貸) 備品減価償却累計額 80,000
4. 給料の未払い
- 今期に発生しているが、まだ支払っていない費用を計上します。
- (借) 給料 30,000 / (貸) 未払給料 30,000
- (借) 給料 30,000 / (貸) 未払給料 30,000
【ステップ2】精算表を作成する
ステップ1の仕訳を基に、精算表の各欄を埋めていきます。
- 試算表欄:問題の「決算整理前残高試算表」の金額をそのまま書き写します。
- 修正記入欄:ステップ1で行った「決算整理仕訳」を転記します。
- 仕訳の借方に来た勘定科目の借方欄に金額を記入します。
- 仕訳の貸方に来た勘定科目の貸方欄に金額を記入します。
- 試算表にない勘定科目(貸倒引当金繰入など)は、下の空いている行に追加して記入します。
- 損益計算書欄:収益と費用に分類される勘定科目の金額を転記します。
- 試算表欄と修正記入欄の金額を合算(または相殺)した最終的な金額を記入します。
- 例:給料 = 試算表 ¥320,000 (借) + 修正記入 ¥30,000 (借) = 損益計算書 ¥350,000 (借)
- 貸借対照表欄:資産、負債、純資産(資本)に分類される勘定科目の金額を転記します。
- こちらも、試算表欄と修正記入欄の金額を合算・相殺した最終金額を記入します。
- 例:繰越商品 = 試算表 ¥200,000 (借) – 修正記入 ¥200,000 (貸) + 修正記入 ¥300,000 (借) = 貸借対照表 ¥300,000 (借)
- 当期純利益の計算:
- 損益計算書欄の貸方合計(収益)と借方合計(費用)の差額を計算します。
- 貸方合計 > 借方合計 の場合、その差額が当期純利益です。損益計算書欄の借方と、貸借対照表欄の貸方にその金額を記入します。
- 最後に、損益計算書欄と貸借対照表欄の借方・貸方の合計がそれぞれ一致することを確認します。
学習のポイントや注意点
- ポイント:ケアレスミスこそが最大の敵です 。電卓の打ち間違い、転記ミスを防ぐため、指差し確認や声に出しての確認を練習段階から習慣づけましょう。
- 時間管理:もし貸借対照表の貸借が一致しなくても、深追いしすぎない勇気も必要です。部分点は狙えるため、一つのミスに固執して時間を浪費するより、他の問題の見直しに時間を使いましょう。
- 精算表は慣れが必要です。この問題を何度も解きなおし、手順を体に覚え込ませることで、本番の試験でもスムーズに、かつ正確に解答できるようになります。頑張ってください!
結論:簿記3級合格に向けた最終戦略
日商簿記3級の合格を確実にするためには、知識のインプットだけでなく、試験形式に特化した戦略的なアウトプット練習が不可欠です。最後に、本番で実力を最大限に発揮するための最終戦略をまとめます。
各大問の最終チェックポイント
- 第1問(仕訳問題):取引を「5要素の増減」に分解する体系的な分析プロセスを体に染み込ませてください。これができれば、45点満点も夢ではありません。スピードを意識し、1問1分程度で解けるように反復練習を重ねましょう 。
- 第2問(勘定記入・補助簿):仕訳データがT勘定や各種帳簿へどう「流れていくか」を常に意識することが攻略の鍵です。満点を狙うのではなく、確実に取れる部分点を拾っていく戦略で臨みましょう。
- 第3問(決算整理):厳格なワークフローを守り、ケアレスミスを徹底的に排除することがすべてです。「決算整理仕訳 → T勘定で残高更新 → P/L作成 → B/S作成 → 最終チェック」という手順を、どんな問題でも踏襲してください。
ネット試験(CBT)に特化した対策
現在の主流であるネット試験には、特有の注意点と対策が存在します。
- 時間配分戦略:試験時間は60分と非常にタイトです。多くの上級者が推奨する解く順番は「第1問 → 第3問 → 第2問」です 。得点源である第1問と第3問に十分な時間を確保し、残り時間で第2問に取り組むのが最も効率的です。目標時間は、第1問:15〜20分、第3問:25〜30分、第2問:10〜15分を目安にしましょう。
- デジタル操作への習熟:ネット試験では、勘定科目をプルダウンメニューから選択し、金額をキーボードで入力します 。普段からパソコン操作に慣れていない方は、オンラインの模擬試験などを活用し、本番のインターフェースに慣れておくことが重要です 。
- 計算用紙(メモ用紙)の活用法:試験画面に直接書き込みはできません。配布される計算用紙をいかに効率的に使うかが勝負を分けます 。特に第2問や第3問では、あらかじめT勘定の枠や精算表の簡単な骨組みを書き出しておくと、思考を整理しやすくなります。
最後に
簿記3級は、正しい学習法と戦略的な練習を続ければ、誰でも必ず合格できる資格です。初めて見る専門用語に戸惑うこともあるかもしれませんが、一つ一つの取引が実際のビジネスシーンでどのように行われているかをイメージすることで、理解は格段に深まります 。
本ガイドで学んだ解法プロセスを武器に、数多くの問題演習をこなし、自信を持って本番に臨んでください。あなたの努力が実を結ぶことを心から応援しています。