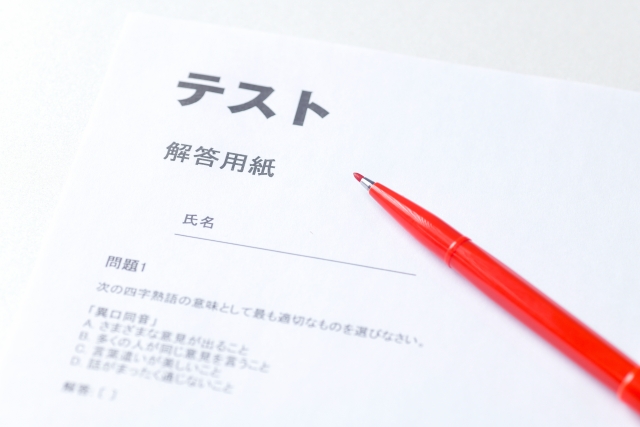国語のテストで、「よし、この問題の答えは、本文のこの辺りに書いてあるぞ!」と確信を持ったのに、いざ答えを書こうとすると、「あれ、ぴったり〇字に収まらない…」「どの言葉を使えばいいんだろう?」と、手が止まってしまった経験はないかしら。
「本文中から〇字で抜き出せ」
この形式の問題は、国語が得意な子でも、意外と失点しやすい落とし穴なの。でもね、見方を変えれば、これは答えが必ず本文の中に眠っている「宝探しゲーム」。自分であれこれ考えて文章を作る必要がない、とっても親切な問題なんだよ。
今日は、その宝物を素早く、そして正確に見つけ出すための「探偵のルール」と「捜査のコツ」を、君に伝授します。この方法を身につければ、抜き出し問題は君にとって、確実に点数を稼げる得意分野に変わるはずよ。
「本文中から〇字で抜き出せ」問題、探すコツとルール
まずは、このゲームの絶対に守らなくてはいけない「ルール」から確認しましょう。これを破ると、せっかく宝物を見つけても失格になってしまうからね。
大前提!抜き出し問題の「3つの鉄則」
鉄則①:絶対に、本文の言葉を「そのまま」書き写す これが一番大事。「抜き出せ」という指示は、「本文と一字一句同じ言葉を写しなさい」という意味です。自分で言葉を足したり、変えたり、漢字をひらがなに直したりするのは絶対にダメ。「〜ということ。」と書かれているのに、「〜こと。」と句点を省略するのも不正解。とにかく、本文を忠実にコピーすることだけを考えて。
鉄則②:句読点(、。)や記号(「」)も、すべて一字として数える 見落としがちなのが、句読点やカギかっこの存在。これらも、ちゃんと一文字分のスペースを持っている大切なキャラクターです。
(例)「すごいね。」 → 「(1) す(2) ご(3) い(4) ね(5) 。(6) 」(7) の7文字です。カギかっこはセットで数えるのではなく、始めと終わり、それぞれで数えることもあるから、問題の指示をよく見てね。
でも基本は、「(1) は(2) い(3) 。(4) 」(5) で5文字と数えるのが一般的よ。
鉄則③:字数は、ヒントではなく「絶対条件」 「だいたい〇字くらい」ではありません。「〇字」と指定されたら、その字数にぴったり合う言葉が、本文のどこかに必ず隠されています。字数が合わないと感じたら、それは君の探し方が間違っているというサイン。探し直す勇気を持って。
宝の地図を読み解く!答えを探す「3つのコツ」
ルールを覚えたら、いよいよ宝探しの実践的なコツを見ていきましょう。
コツ①:傍線部の「すぐ前・すぐ後ろ」を徹底的に探る! これが一番の近道。ほとんどの問題(8割以上!)は、傍線部のすぐ近くに答えが隠されています。筆者は、読者が分かりやすいように、質問の対象となる言葉のすぐ近くで、その説明や理由を述べていることがほとんどなの。 文章全体を闇雲に探す前に、まずは傍線部を中心とした前後2〜3行を、虫眼鏡で見るようにじっくりと捜査してみて。
コツ②:質問の中の「キーワード」と同じ言葉を、本文で探す! 次に注目するのは、設問の文章そのもの。 例えば、「筆者が問題だと考えているのは、どのようなことですか。」と聞かれたら、君が探すべき宝のヒントは「問題」というキーワード。 本文の中から(特に傍線部の近くから)、「問題」という言葉や、「課題」「欠点」「〜する必要がある」といった、似た意味の言葉を探し出すの。その周辺に、答えが潜んでいる可能性が非常に高いわ。
コツ③:質問の「文末」と、答えの「文末」を合わせる! これは、少し上級者向けのテクニック。質問のされ方と、本文中の答えの文末の形は、しばしば綺麗に対応しています。
- 質問が「〜はなぜですか。」(理由)の場合
- → 答えの文末は「〜からだ。」「〜ためである。」となっていることが多い。
- 質問が「〜とは、どういうことですか。」(説明)の場合
- → 答えの文末は「〜ということだ。」「〜のことである。」となっていることが多い。
このパターンを知っていると、「あ、ここに『〜からだ。』がある!ここが理由だ!」と、宝のありかをピンポイントで特定できるようになるよ。
橘先生からのメッセージ
抜き出し問題は、君の読解力というよりも、むしろ「丁寧さ」と「正確さ」を試す問題です。焦る気持ちをぐっとこらえて、「ルールとコツ」という探偵の道具を冷静に使えるかどうか。
これは、言葉を大切に扱う訓練でもあるの。筆者が選び抜いた言葉を、一字一句おろそかにせず、正確に捉える。その誠実な姿勢が、君を正解へと導いてくれます。
練習すればするほど、宝探しのスピードと精度は確実に上がっていくわ。一つひとつの言葉を大切に扱いながら、落ち着いて宝物を見つけ出せる、名探偵になってちょうだいね。先生、応援しているよ。